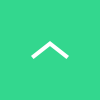ミトサンが気になる表現者たちの素顔に迫るパーソナルインタビュー。今回は年間50本以上のミュージックビデオを制作する映像ディレクター、加藤マニさんをお迎えしました。
ミュージックビデオの世界では異色の存在。企画、撮影、演出、編集をほぼ一人で手がけるスキルとセンスに加えて、予算を含めたクライアントの要望に可能な限り応えてくれる安心感。自身もミュージシャンなので、バンド仲間や業界関係者からの信頼も厚い。そんな加藤マニが、年間50本以上のペースで新作ミュージックビデオを作れるのはどうしてなのか? そのヒントを見つけるパーソナルインタビュー。前編は学生時代の話をメインに語ってもらいました。
高3の時の文化祭で将来の道が決まった感じです
加藤マニ(以下、加藤) 地元が青梅なんですが、その中でも特に田舎の、山が邪魔でBSやCSなどの衛星放送が受信できず、川が邪魔でケーブルテレビも届かないっていう地域に住んでまして。
中学生のある日、アンテナが傾いたのか、無料視聴期間サービスだったのか分からないものの、たまたまスペシャ(スペースシャワーTV)が見れるようになったんです。それまで音楽チャンネルの存在をまったく知らなかったから、衝撃を受けて。その時に流れていたのが、ナンバーガールの「鉄風 鋭くなって」で、これがとにかくカッコよかった。
冒頭に曲タイトルがドーン!と出てきて。いま考えると、当時は他にもカッコいいMVがたくさんあったんですよね。ひたすらズームと引きを繰り返すTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTの「カルチャー」とか、演奏シーンではなく、リリカルな映像やドラマで見せるSUPERCARの「WONDER WORD」や「BE」とか。

加藤 2週間くらいだった気がします。
加藤 はい。でも、ほとんど何もしてなかったです。テキストサイトとかにハマっていれば別だったのかもしれませんが、任天堂のオフィシャルサイトを眺める程度で。当時は、インターネットはそんなに面白いものだと思ってなかった気がします。中学生時代はまだ音楽自体にあまり興味がなく、それこそ『COUNT DOWN TV』でちょっと聞こえてくる程度で、CDもそんなに買ってませんでした。
加藤 中学生の時は映像部に所属しておりまして、映画研究部みたいなイメージで入部したんですが、ぜんぜん違いました。ガタイの大きいオタクと、小さいオタクが一個上に一人ずついて、あとはわたしを含めて数人。なんていうか、稲中みたいな状態で。
加藤 いわゆる「イケてないわたしたち」って状態だったんですが、そんな面々が他の生徒の映像を撮るんです。新入生に見せるための様々な部活動紹介、全クラスの合唱祭の様子など、機材環境はそれなりに恵まれてましたが、これって職員がやることじゃねえかって。
加藤 まあ、好きにやらせてもらえましたし、自分も3年生になって部長になったんですよ。ある日、部活動紹介のムービーを撮る時に面白がっていろいろやってたら、終わりの時間をオーバーしてしまって。その後、顧問の先生に怒られてしばらく休部にすると言われたんです。なんでやねん!と思って、もともとやる気があったわけでもなかったのであっさり廃部にしました。で、陸上部に行くことにしたんです。
加藤 そうなんです。
加藤 仕事っぽい感じでしたね。楽しい思い出はあんまりないです。他のクラスの合唱の映像を律儀に全部チェックしたりとか。
加藤 結構楽しかったです。自分で思ってたよりも自分の足が速かったという事実を知って、高校では陸上部に入ったんですよね。
加藤 いや、陸上をしつつ、ビデオカメラは持っていたので、いろんな動画を撮ってました。3年生の時の文化祭で、クラス仕切りの出し物とは別に個人で発案して上映会をやったんですが、その時に将来の道がなんとなく決まった感じです。高校が立川だったんですけど、立川の街をずっと後ろ向きで歩いて、それを逆再生するとか。その映像に合わせてレッチリの曲を流したり、『ジャッカス』みたいな動画をたくさん作ってました。
加藤 たぶん、いま自分で言うのは恥ずかしいんですが、その当時は映像作家になりたかったんだと思います。でも、今は映像作家って呼ばれるのは辛い(笑)。何か恥ずかしいです。その時はそういう言葉としてでしか説明できなかったんでしょうね。自分のやりたいことが。
パソコンとカメラさえあれば映画が撮れるってことを学べた
高校卒業後は早稲田大学川口芸術学校という専門学校に行かれるんですよね。
加藤 日芸(日本大学芸術学部)単願で受けてコケて、自分の中で「ブックオフ暗黒時代」と呼んでる1年を過ごし、それから専門学校に進学したんです。加藤家の謎ルールなんですが、日芸の受験で学科をクリアして、その後の面接で落ちた場合、次の年に専門を受けてもいいことになっていて。母親はやっぱり大学に行って欲しかったみたいなんです。学科をクリアしなくてはいけないのは、普通の大学には入れる程度の学力があることは確かめたかったんでしょうね。果たしてわたしは見事に学科をクリアして面接で落とされたので、そのルールのおかげで専門学校に入ることができました。

専門学校はどうでしたか?
加藤 絶対に学校の中では一番になろうと思ってました。そこで一番になれないようじゃ、もうダメなんじゃないかと思ってしまって。学校ではドキュメンタリーやアニメーション、モーショングラフィックなどに触れつつ、3年になったらゼミを一つ選んで何か作りましょうという流れだったので、映画だけ作りたい人には、何故やらなきゃいけないんだろうというカリキュラムもあったと思うんですけど、自分にとっては種目みたいな感じでした。陸上で言う七種競技というか、どのカリキュラムも一番いい結果を残したい気持ちはあったから、他の学生の作品を見て「負けた」って思うとすごく悔しかった。基本的にはあいつが毎回一番いいっていう雰囲気を受けていたかったので。
他の生徒で「こいつは凄い!」って思う人はいました?
加藤 同級生に奥田くんという人がいて、2011年に『東京プレイボーイクラブ』で商業映画デビューした映画監督の奥田庸介さんなんですよ。彼は凄かったです。デジタル機材にほとんど触ったことがないけど、とにかく映画を撮りたいという情熱と、天然スカムなセンスが炸裂して、どんなものもめちゃくちゃ面白い状態になるんです。ホームページを作ってみましょう、みたいな授業があって、彼は敬愛するロニー・コールマンっていうボディビルダーの画像をとにかくたくさん並べるんですよ。さらに背景を黒くしようとしてphotoshopのペンキツールを使ったら、人物も背景も黒くグチャグチャになってしまった。でも、そのグチャグチャさが何とも言えず悲惨なユーモアというか、とにかく面白い。狙って成功している感じではないのに、結果的に特別賞をもらえるくらいの盛り上がりが常にあり、そういう意味でも別格でしたね。
奥田さん含め、学校の生徒たちと一緒に過ごす時間も多かったのでは?
加藤 授業でチームを組んだりすることもありましたが、飲み行こうぜ~みたいにはあんまりならなかったです。そんなことをするために学校に通ってるんじゃない!という感じで、俗に言う意識高い系というか、何か固かった気がしますそのあたり。
じゃあ、ストイックに勉強してたんですね。
加藤 そうですね。割とストイックにやってた気がします。でもバンド活動はしていたので、そっちで楽しんでいた気もします。
当時、映像の学校で勉強したことって、いまでもすごく役立ってるなという実感はあります?
加藤 デジタルシネマについての勉強が多かったので、それは絶対に良かったと思ってます。フィルムを切って貼るみたいな作業はインディでは簡単にできないし、それを突き詰めるとどんどん貧乏になってしまいかねないというか。パソコンとカメラさえあれば映画が撮れるってことを学べたのは大きかったです。あと2005年にYouTubeが出てきて、一人でも動画が作れるという潮流が出来つつあって、いきなりディレクターとして世に出て行くことが可能になりつつある空気もあった。

タイミングも良かったと。
加藤 そうなんですよね。それはラッキーでした。
卒業後は映像のプロダクションに入って、すぐやめちゃうんですよね。
加藤 そうです。当時活動していたバンドが楽しくて、今から思うとぜんぜん売れる感じではなかったんですが、その時は「なんかいけちゃいそうじゃないですかこれ~」っていう雰囲気になっていて。頭の中はロックンロール状態なのに、毎日決まった時間に出社して、寒い部屋の中でずっとテープのダビングをさせられる。撮影の現場に行くわけでもなく、最初はずっとそれだけなんです。いい会社ではあったんですが、自分はこういうの向いてないなと思って。
美容師も見習い期間はずっとシャンプーしかできないですからね。我慢すれば、いずれ現場に出られたかもしれない。
加藤 そう、だから下積みとして当然の話ではあるんですけど、自分としてはなんかダメでしたね。ある日、友達の写真展を見に原宿に行くことがあって、仕事の帰りか何かで原宿の交差点をスーツ着て歩いてたんですが、突然思ったんですよ。なんかダサい!って。原宿でスーツ着て歩いてる今のわたし、猛烈にダサいぞって。
(笑)当時はファッションスナップの人たちで原宿界隈は盛り上がってましたからね。
加藤 その時、実家の青梅から職場の赤坂まで通ってたんです。一人暮らししろよって話なんですが、とにかく遠いんですよ。ある時、国分寺駅が火災か何かで、電車がまったく動かなくなったことがあって。そしたら、たまたま高校の頃の同級生がクルマで駅まで来ていたから、そのまま遊びに行っちゃったんですよ。で、4時間くらい遅れて会社に着いて……みたいなこともあったりして、これはもう辞めようかなぁと思って、結局20日間でドロンしました。会社には父親が倒れてしまって、実家の紙コップ工場を継がないといけなくなったと言って。
お母さんには何か言われなかったですか?
加藤 母には必要以上にブラック企業で大変なんだという一面を強調していたので、逆にすごく心配かけてしまいました。その時はウソばっかりついてたんですよ。この記事を読まれたら怒られそうですが、仕事は定時に終わっているのに、友達のライブに行ってから終電ギリギリで家に帰ってました。でも家では、こんな時間まで会社に働かされていたというアピールをして。
なかなかゲスい話ですね(笑)
加藤 なので母親的には辞めてもらってむしろ安心したっていう感じで。で、実家から出ることにしました。
そう考えると、辞めて正解だったかもしれませんね。
加藤 そうしないと腐っていっただろうなと思いますね。同期の皆さんの負担が増えていたりを考えると非常に申し訳ない気持ちもありましたが。

いまのマニさんのキャリアがあるから笑える話題ですけど、そうじゃなかったらただのクソ野郎で終わるところでしたね(笑)。
加藤 正にそうです。クソ野郎の入り口でした(笑)。そうならないように、まずは実家を出ることにしたんです。
※後編につづく
加藤マニ
1985年8月14日生。東京都青梅市出身。1995年の夏、自由研究の題材としてコマ撮りアニメーションを選び、ハムスターのイラストを書いた紙を切り抜き、父親の持っていたVHS-Cカセットのビデオレコーダーで1コマずつ撮影したことから映像制作に興味を持つ。2014年、冨田ラボ「この世は不思議 feat. 原 由子、横山剣、椎名林檎、さかいゆう」にて、SPACE SHOWER TV MUSIC VIDEO AWARD 2014 BEST VIDEO受賞。2015年、キュウソネコカミ「ビビった」にて、SPACE SHOWER TV MUSIC VIDEO AWARD 2015 BEST VIDEO受賞。2016年秋、マニフィルムス株式会社として法人化。現在は東京・代田橋の不気味なマンションを本拠に、映像監督 奥藤祥弘、大眉俊二、CGデザイナー 石原大毅らと共にWAHを結成。インディーズ、メジャーを問わずミュージックビデオ等の映像制作、広告デザインやウェブデザインをおこなう。